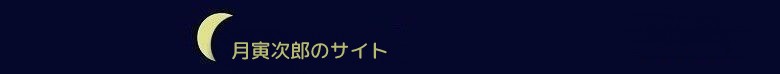
全面タッチパネルと物理ボタン付(カーナビの選び方)
全面タッチパネルと物理ボタン付(カーナビの選び方)

物理的なボタンが付いているカーナビと、全面タッチパネルでボタンが一切ないモデルは、どちらがおすすめでしょうか?
個人的な好みもあると思いますが、ステアリングスイッチの有無も判断材料の一つです。
ナビ交換と取付の目次(自分でDIY)
- ナビ交換・取付(メインページ)
- カーナビの選び方
- ATOTO A6G209PFを購入
- ATOTO S8G2094MSを購入
- インパネ外し(鏡を使ってカプラを楽に外す)
- ナビロックボルト取り外し
- カーナビの配線・接続ケーブルの確認
- カーナビ専用ハーネスの自作
- ギボシ端子のかしめ方(よくある失敗と対処)
- カーナビ作動確認(仮接続)
- GPSアンテナ取付
- カーナビ取付 ステー装着
- カーナビ取付 インパネカット加工
- カーナビ取付 配線接続、固定
- ファームウエア更新(ATOTOナビ)
- ATOTOナビ設定(記録しておくと役に立つ)
- 使用後レビュー(Carplayナビ、メリットは大きい)
- Androidカーナビ、気になる点(今後の改善に期待)
- 車で使っているアプリ
ステアリングスイッチ装着車の場合、全面タッチパネルがおすすめ
ステアリングスイッチ付きの車両の場合、物理ボタンの無い全面タッチパネルのモデルがおすすめです。音量ボリューム操作と選曲(選局)に関しては、リモコンボタンで操作可能ですので、ハンドルから手を離さずに操作できます。
そのため、本体側で音量調節や曲送りを行うことは、まずありません。
なお、ステアリングスイッチ非装着の場合でも、後付けの汎用Bluetoothリモコンを使えば、同様の機能は実現可能です。
(下記リンク先ページの下の方で紹介しています)
● 関連ページ:ステアリングスイッチ
(ディスプレイオーディオとの接続、および、スイッチ機能を学習させる手順)
全面タッチパネルのメリット
さらに全面タッチパネルには、さまざまなメリットがあります。- 真っ平らなので、画面の拭き取り掃除が楽
- ホコリの溜まりがちな、奥まった隅の部分が無い
- 物理的な接点を介することによる、電子的接触不良が発生しない
- 長く使用していると、頻繁に触るボタンは表面にテカりが出て古びてくるが、そのような経年ヘタリが生じない
- 保護フイルムを貼れば、新品同等の状態を維持可能で、リセールバリューも高くなる
ATOTO用保護フィルム を見てみよう
● ATOTO 保護フィルム (amazonで検索)
● ATOTO 保護フィルム (楽天で検索)

ちなみに、筆者が使っているのは、全面タッチパネルのA6G209PFです。
筆者の車はステアリングスイッチ装着車ですので、全面タッチパネルのモデルを選択しました。
音量調節と曲送り(曲戻し)は、ハンドルのスイッチで操作可能ですので、液晶画面下部のタッチスイッチを操作することは、全くありません。
● ATOTO A6G209PF(amazon 商品ページ)
● ATOTO A6G209PF(楽天で安い順に検索)

ATOTOには、他にも多数の全面タッチパネルモデルがあります。
製品型式からは、物理ボタンモデルか、全面タッチモデルかを判別することはできませんが、製品外観で一目瞭然なので、特に問題ないでしょう。
※ 厳密には、型式の5桁目が『A』の場合は「物理ボタン」、『B』なら「全面タッチパネル」であることが多いですが、どちらにも当てはまらないモデルも存在するため、一概には言えません。
ボタンの有無で、候補機種を絞り込もう
ボタン付きのモデルが良いのか、ボタン無しが良いのかを決めることで、カーナビの候補機種が大きく絞られてきます。自分に最適なディスプレイオーディオを選ぶのも楽になりますので、画面サイズや、搭載OSと同様に、早めに決めておくと良いです。
個人の好みもあるため一概には言えませんが、携帯電話を例に上げると、
ボタンが沢山付いたガラケーの方が使いやすいという方は、従来型の物理ボタン付きカーナビを、
タッチパネル操作のスマホの方が好みだという方は、全面タッチパネルのディスプレイオーディオを選択すると良いでしょう。
ボタンの有無で、製品イメージも大きく変わりますので、見た目の好き嫌いで決めるのも一つの方法です。
下のリンクにある「F7・A6・S8 徹底解説」ページでは、各製品ごとのスペック比較表を掲載しています。
この一覧表の中で、「タッチ」「物理」とあるのは、それぞれ「全面タッチパネル」と「物理ボタン付き」のモデルことです。(最適なカーナビ選びに使ってください)
● 関連ページ:ATOTO F7 徹底解説
● 関連ページ:ATOTO A6 徹底解説
● 関連ページ:ATOTO S8 徹底解説
ステアリングスイッチ非装着車は、物理ボタン付きがおすすめ
ステアリングスイッチ非装着車の場合は、物理ボタン付きのモデルがおすすめです。(ボタンの位置に慣れてしまえば)音量調節や曲送りなどの操作を手探りでできるため、前方から目を離さずに操作が可能です。
全面フラットパネルのカーナビの場合は、(道路状況から目を離し)画面に視線を持っていかなければ、どこにタッチボタンがあるか判りません。
前を見ながら操作することは難しいです。
このような理由で、ステアリングスイッチ非装着車の場合は、運転時の安全性を高めるためにも、物理ボタン付きのモデルがおすすめです。
(走行中にカーナビを操作することはない(停車時にしか操作しない)という方は、この限りではありません)

ATOTO A6G2A7PFは、物理ボタン付きの7インチモデルです。
国内メーカーのモデルと比較すると、価格が一段階安く、Androidナビとしては最低価格帯に位置することもあり、手堅い人気のあるモデルです。
● ATOTO A6G2A7PF (amazon 商品ページ)
● ATOTO A6G2A7PF (楽天で安い順に検索)

このS8G2109UPというモデルは、見てわかる通り、音量と曲送りにシーソー型のボタンが採用されています。
このキー形状は、手探りでも指の感覚でわかりやすいのが良いところです。
● ATOTO S8G2109UP(amazon 商品ページ)
● ATOTO S8G2109UP(楽天で安い順に検索)
● ATOTO S8G1109UP(S8G2109UPの新型・ATOTO公式楽天市場店)
路面のみを注視した状態で、車内に視線を動かさずに、どれだけ確実に操作可能かというのは、自動車の運転のしやすさの一つのポイントでもあります。
これを「手探り操作性」という言葉を使って表現した自動車評論家の方がおられますが、「見ないでも操作できる」ということは、運転における重要ポイントの一つです。
最近の車では、カーエアコンの操作をタッチパネルで行う車が増えてきましたが、一部の方々に不評を買っています。
温度の上げ下げや風量の増減については、ノブ型(つまみ式)の方が扱いやすく、走行中でも手探りで操作できるからです。
(頻繁に停車する市街地であれば良いのですが、高速道路などでは、この「手探り操作性」の良否が、安全性に大きく影響を及ぼします。脇見運転防止の一助となるからです)
ボタンではなく「ノブ」、手探りでも操作がしやすい

ボタンよりもさらに直感的に操作が可能な『ノブ』が付いたモデルも存在します。
F7TYC7XEは、今時珍しいボリュームノブ付きのモデルです。
高齢者でも直感的に操作できるため、不特定多数の人が運転する車に良いでしょう。
サイズが7V型(7型ワイド)ですので、現場仕事に使うハイエース、営業用のプロボックス、軽貨物のハイゼットカーゴ、農作業用のハイゼットなどにぴったりです。
● ATOTO F7TYC7XE(楽天で検索)
感圧式パネルと、静電タッチパネル
ここで、感圧型パネルと、静電タッチパネルの違いにも触れておきましょう。感圧式タッチパネル
感圧式はその名の通り、パネルを押す圧力を検知して反応するタッチパネルです。圧力の有無がポイントですので、ごく軽く触れた場合には反応しません。
このため、わずかですが「押す」感じで操作する必要があります。
また、感圧型タッチパネルのデメリットとして、経年変化によってタッチ位置の判定にズレが生じることがあります。
(電気的な抵抗値で位置判定しており、経年によって抵抗値に変化が生じることが原因です)
静電容量式タッチパネル
一方の静電容量式タッチパネルは、押し込む必要がなく、軽く触れるだけで操作可能です。ピンチアウトやスワイプ、タッチジェスチャーなど、多彩な操作が可能なのも、このタイプです。
タッチジェスチャー等はあくまでも原理的に可能なだけであって、機器側のユーザーインターフェースが対応していない場合は、この限りではありません。
近年発売されたモデルでは、対応していることが多いですが、購入前に確認しておくと良いでしょう。
ちなみに、ATOTO製品は、非常に多彩なタッチジェスチャーが可能です。
現在は静電式が主流
カーナビ用のタッチパネルは、以前は感圧型が主流でしたが、今では静電式タッチパネルが主流となりつつあります。個人的には、以前使用していたカーナビが感圧式であり、タッチ位置のずれに悩まされることもしばしばでした。
ナビを「ATOTO A6G209PF」に交換し、静電タッチパネルを操作するようになってからは、反応が軽く、サクサク動くため、ストレスフリーです。
(音声入力の精度も高いですので、目的地入力時にタッチ操作を行うことも減りました)
現在販売されているカーナビのタッチパネルは、静電容量式が主流となっていますが、従来型のモデルは感圧式の場合もあります。
カーナビを購入する際には、タッチパネルが感圧式か静電式か、事前に確認しておきましょう。
基本的には静電式がおすすめですが、手袋をした状態で操作することが多い場合は、「感圧式」を選択するのも一つの方法です(静電式では反応しないため)
カーナビ ランキング(amazon / 楽天)
● カーナビ ランキング (amazon)
● カーナビ ランキング (楽天)
● ATOTO製品一覧(amazon)
次ページ: ATOTO A6 S8 F7 比較と違い
ナビ交換と取付の目次(自分でDIY)
- ナビ交換・取付(メインページ)
- カーナビの選び方
- ATOTO A6G209PFを購入
- ATOTO S8G2094MSを購入
- インパネ外し(鏡を使ってカプラを楽に外す)
- ナビロックボルト取り外し
- カーナビの配線・接続ケーブルの確認
- カーナビ専用ハーネスの自作
- ギボシ端子のかしめ方(よくある失敗と対処)
- カーナビ作動確認(仮接続)
- GPSアンテナ取付
- カーナビ取付 ステー装着
- カーナビ取付 インパネカット加工
- カーナビ取付 配線接続、固定
- ファームウエア更新(ATOTOナビ)
- ATOTOナビ設定(記録しておくと役に立つ)
- 使用後レビュー(Carplayナビ、メリットは大きい)
- Androidカーナビ、気になる点(今後の改善に期待)
- 車で使っているアプリ
サイトのトップページ